外で猫を散歩させているといろんな生き物に出会います。
なんとこのたび「細長いカタツムリ」をみつけました。
▼こちら。

「キセルガイ」と言うようです。
実は以前からからっぽの小さな巻貝を庭で目にしていました。当時は「昔ここは海でその名残なのかな?」なんて適当なことを思っていました。公園の砂場なんかにもこのような細い貝が混ざっているときがありますよね?
でも実はちゃんと中の人(?)がいました…。
ある日モゾモゾと貝が動くので「なんだ?」と思って注意深く見てみるとカタツムリみたいに動いているではありませんか。そういうわけで今回やっと殻の主と会えたわけです。
今回は「キセルガイ」を深掘りしていきます。
細長いカタツムリ正体は「キセルガイ」
▼キセルガイ(煙管貝)です。

昔のたばこ「キセル」に似てるからだとか。(似てるか?)

細長い貝なので歩きにくそうでした。
丸い殻の比較的コンパクトなカタツムリよりも身動きをとるのが難しそうなキセルガイ。大丈夫かなあ?と心配になります。しかしここまで淘汰されずに生き残っているということは大丈夫なのでしょう。
見つけた場所は木の葉などが落ちている陰になった湿った場所です。見ての通りカタツムリの仲間。私が見たものは貝の長さが1㎝くらい。
繁殖方法
温度が20度~30度ほどでキセルガイの繁殖が活発になります。
キセルガイは雌雄同体ですが別の個体と交尾をします。一般的には卵を体内でふ化させて子を産む繁殖形態です。(卵胎生)
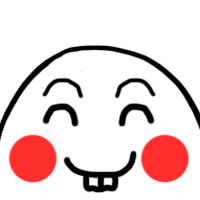
グッピーは卵胎生で有名ですね。
ちなみにキセルガイの赤ちゃんは貝付きで生まれてきます。これはカタツムリもそうです。
生息地
- 西日本から南西諸島にかけて生息・北日本には少ない
- 日本には200種ほどのキセルガイが存在・中には絶滅の恐れのある種類もいる
生態
- 高温や乾燥にも強いが湿った場所で過ごす
- 食べ物は落ち葉や木の表面についている藻や菌類
- 寿命は種によって違うが長くて10年
民間療法にも使われるキセルガイ
福島県ではキセルガイを肝臓の薬として使用しています。
エスカルゴという料理あったり、ナメクジは漢方薬にも用いられたりするくらいですのでキセルガイを口にすることはさほど驚くことでもないです。

効くんだろうか…
他にも地域ごとに信仰があるようです。
まとめ
細長いかたつむりの正体は「キセルガイ」だった!
猫を外で散歩させているといろんな生き物に出会い面白い発見があります。この記事を書いている今の季節(5,6月)は絶賛ダンゴムシ祭りですが…。
【あわせて読みたい】
【幼虫嫌いは閲覧注意】キアゲハの幼虫を見つけました!食べ物や特徴は?
猫に散歩は必要?散歩する際の注意点、メリット・デメリットとは?
▼「自然は楽しい!自然をもっと感じたい知りたい!」と言う方にオススメのネイチャーロハス漫画「とりぱん」。鳥以外にもさまざまな生き物を面白おかしく、ときにはしっとりと描かれています。(これがたまらない)個人的にこの先絶対に手放さないであろう漫画の一つです。



